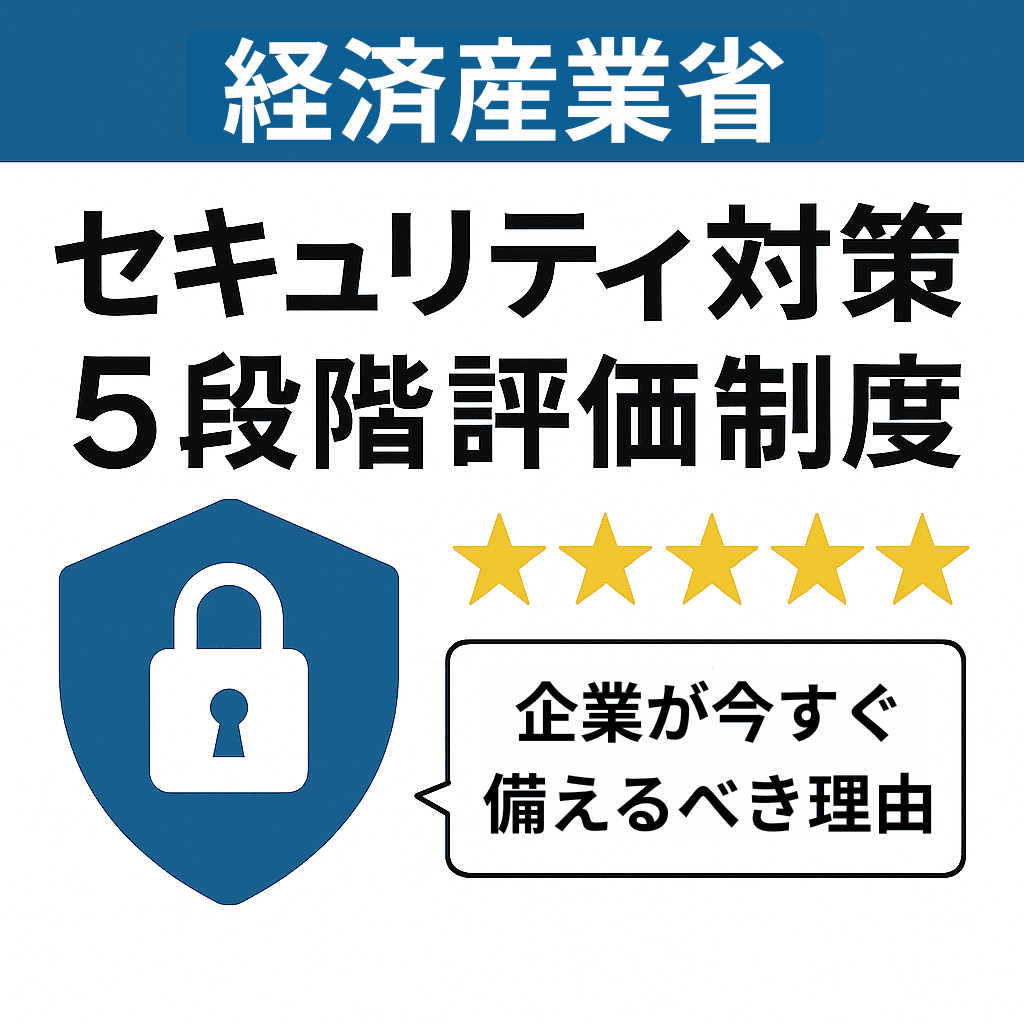はじめに:企業のセキュリティ対策が「評価される時代」へ
近年、サイバー攻撃の高度化と拡大により、企業のセキュリティ対策はもはや“自己責任”では済まされないフェーズに突入しています。特に、サプライチェーン全体に影響を与えるインシデントが増えており、発注元企業にとっても取引先企業のセキュリティ対策は極めて重要な評価ポイントとなりつつあります。
こうした背景を受け、経済産業省は2026年度下期より、企業のセキュリティ対策を★3~★5の3段階で評価する新制度「セキュリティ対策評価制度(仮称)」の導入を発表しました。
本記事では、この制度の概要から導入理由、企業が取るべき具体的な対応、そして導入のメリット・リスクまでを解説し、自社での活用可能性について検討するヒントを提供します。
※サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度構築に向けた中間取りまとめ(2025/04/14 経済産業省)
第1章:セキュリティ対策5段階評価制度とは?
制度の目的
経済産業省が推進する「セキュリティ対策評価制度」は、企業が取引先に対してセキュリティ水準を確認・要求する際の共通指標を提供するものです。サプライチェーン全体のセキュリティレベルの底上げを図ることが目的とされています。
評価基準と★マークの意味
| 評価 | レベル | 特徴 | 評価方法 |
|---|---|---|---|
| ★3 | Basic | 基本的な対策を満たす | 自己評価(25項目) |
| ★4 | Standard | 標準的な対策+ガバナンス対応 | 第三者評価(44項目) |
| ★5 | Advanced | リスクベース・先進的対策 | 高度な外部評価を予定 |
評価の対象領域
-
組織的管理体制(ポリシー、責任体制等)
-
技術的対策(ファイアウォール、EDR等)
-
インシデント対応能力
-
取引先管理とサプライチェーン統制
-
継続的改善活動
第2章:なぜ今この制度が必要なのか?
セキュリティ事故の連鎖被害が深刻化
-
中小企業や下請け企業の脆弱性が、大企業への「踏み台」として悪用されるケースが急増。
-
取引先のセキュリティ事故が企業ブランドや供給責任にも影響。
企業間の信頼を“見える化”する仕組みが求められていた
-
これまで「どれだけ安全か?」を示す基準があいまいだった。
-
経産省が主導することで、業界横断的な信頼指標が確立される期待。
海外取引やサプライチェーン契約での国際的な要請にも対応
-
米国NISTやEUのENISAなど、国際的にも「セキュリティ格付け」は普及中。
-
国内企業が輸出・調達で不利にならないための対応策。
第3章:この制度を導入すべき企業とは?
制度の対象になる企業
-
すでに大手企業との取引がある、または今後取引を目指す中堅・中小企業
-
製造業・医療・IT・建設・物流など、多様な業種が対象
-
SaaSベンダーやクラウド事業者など、ITインフラを提供する企業も含まれる
導入が強く推奨される企業の特徴
-
発注元企業から「セキュリティ水準の開示」を求められたことがある
-
ISMSやPマークなどの取得を目指している
-
顧客情報や機密情報を扱う業務が多い
まだ制度対応が不要な企業とは?
-
一般消費者向けの小規模店舗や、社内で外部との接続が極めて限定的な業態
-
ただし将来的にB2Bビジネスを検討している場合は対応を視野に入れるべき
第4章:制度導入にあたって企業が行うべき具体的な作業
1. 評価目標の設定(★3・★4・★5)
まずは自社の事業規模や顧客層に応じて、どの★評価を目指すのかを決定する必要があります。
2. 現状評価とギャップ分析
-
経産省が公開している「評価項目リスト」を用いて、現状のセキュリティ対策を棚卸し
-
特に人材不足や未整備の手順(ログ管理、訓練など)を洗い出す
3. 対策の実施と改善
-
セキュリティポリシーの策定・周知
-
アクセス権限管理の整備
-
インシデント対応訓練の実施
-
EDR導入やログ監視体制の構築
4. 評価取得または申請
-
★3:自己評価フォームを提出
-
★4:第三者評価機関による審査(例:ISMS審査機関、専門認証ベンダー等)
-
★5:詳細は今後公表予定だが、リスクベース評価+外部評価を想定
5. 顧客・取引先への提示
取得した評価を、ホームページやパンフレット、提案資料等に掲載し、信頼性のアピール材料にする。
第5章:企業にもたらすメリットと注意点
導入によるメリット
-
サプライチェーン内での信頼獲得
-
新規受注・入札参加要件を満たせる
-
社内体制の見直しによるセキュリティ事故の未然防止
-
採用面でも「対策に真剣な会社」として評価されやすい
制度利用にあたっての注意点
-
評価を取るだけでは意味がない:「運用の継続」が重要
-
形式的な導入で終わらないために、現場との連携がカギ
-
評価制度は“完了”ではなく“改善の起点”として考えること
第6章:弊社が提供できる支援内容とご相談窓口
弊社は、国内外の情報セキュリティ対策に精通したホワイトハッカーによるコンサルティングを強みとしています・
当社が提供できる支援内容
-
★3~★5の到達支援コンサルティング(評価項目解説、文書テンプレート提供など)
-
ギャップ分析支援(現状調査・リスク可視化)
-
運用手順書や規程類の作成サポート
-
サイバー訓練やEDR/ログ管理ツールの導入支援
-
第三者評価対応の模擬監査支援
こんなご相談が増えています
-
「今のセキュリティ体制で★3を取れるのか?」
-
「★4を取るには何から手をつければ良い?」
-
「取引先に求められていて急いで対応したい」
ご相談はこちらから
→→https://kreuz-corp.co.jp/contact/
制度対応に不安をお持ちの企業様へ
評価制度は義務ではありません。
しかしながら、B2B取引においては“実質的な新基準”として広がる可能性が極めて高いものです。いち早く対応することは、競争優位を築くうえでも重要な一手です。
「自社の状況で何が必要か」「どこから着手すべきか」を整理するには、専門家による助言が有効です。
ぜひ、お気軽に弊社までご相談ください。
まとめ:評価制度は“企業信頼”の通貨になる
今後のビジネスにおいて、セキュリティ対策の水準は企業評価の一部として重視されていきます。単なる情報漏えい対策にとどまらず、信頼・契約・採用・成長の土台となるインフラです。
経営層の皆様におかれましては、ぜひこの制度を“コスト”ではなく“信頼獲得の投資”として位置づけていただきたいと思います。